「最近、物忘れが増えた」「同じことを何度も聞いてしまう」「家族が認知症ではないかと心配」といったことはありませんか?
当院のもの忘れ外来では、加齢による自然な物忘れと、認知症など病的な記憶障害を丁寧に見分け、早期発見と適切な対応を行います。問診や神経学的検査、認知機能検査、必要に応じて画像検査を行い、原因を明らかにして治療方針を立てます。「年齢のせい」と片付けず、気になる症状があればぜひ一度ご相談ください。

もの忘れ

もの忘れ
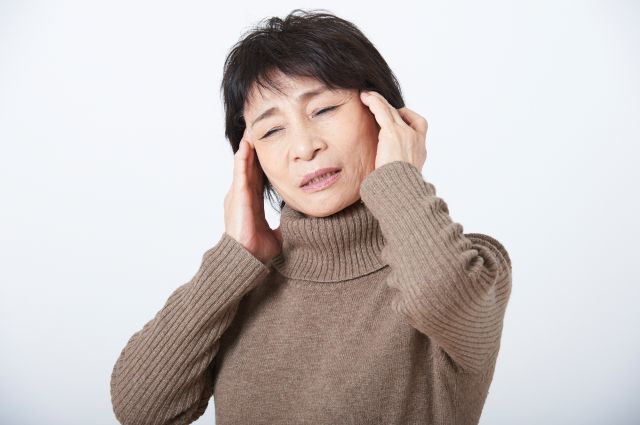
「最近、物忘れが増えた」「同じことを何度も聞いてしまう」「家族が認知症ではないかと心配」といったことはありませんか?
当院のもの忘れ外来では、加齢による自然な物忘れと、認知症など病的な記憶障害を丁寧に見分け、早期発見と適切な対応を行います。問診や神経学的検査、認知機能検査、必要に応じて画像検査を行い、原因を明らかにして治療方針を立てます。「年齢のせい」と片付けず、気になる症状があればぜひ一度ご相談ください。
もの忘れにはさまざまな原因があり、大きく分けて以下のようなものがあります。
加齢によるもの忘れ
(生理的な変化)
年齢を重ねると誰でも「人の名前が思い出せない」「物をどこに置いたか忘れる」といったことが増えます。これは脳の処理速度の低下などによるもので、時間が経てば思い出せることが多く、日常生活に大きな支障はありません。特に治療は必要ありません。
軽度認知障害(MCI)
MCIは、加齢によるもの忘れと認知症の中間にあり、認知症予備軍のような状態です。たとえば、「昨日の食事を思い出せない」「約束を忘れることが増えた」などの症状がありますが、日常生活はおおむね自立して送れます。
認知症によるもの忘れ
認知症の初期症状として記憶障害が現れることも多く、「食事をしたこと自体を忘れる」「同じ話を何度も繰り返す」など、自分では忘れていることに気づかない場合もあります。記憶だけでなく判断力や理解力も低下し、日常生活に支障が出ます。早期に診断することで症状とうまくお付き合いができるようになる可能性があります。
アルツハイマー型認知症
最も多いタイプで、記憶障害から始まり、次第に判断力や理解力も低下していきます。
レビー小体型認知症
幻視(見えないものが見える)や、手足のこわばり・震えなどのパーキンソン症状が特徴です。
前頭側頭型認知症
人格や行動の変化が特徴的で、反社会的な言動が出ることもあります。
脳血管性認知症
脳卒中に関連する認知症です。
正常圧水頭症
歩行障害・尿失禁・認知症が三大症状です。シャント手術により改善が見込める場合もあります。
慢性硬膜下血腫
頭部外傷のあとにゆっくりと血がたまり、脳を圧迫して認知症様症状を引き起こします。外科的処置で改善します。
脳神経内科専門医および日本認知症学会認定専門医・指導医が在籍し、専門的かつ丁寧な診療を行っています。認知症の早期診断・治療に力を入れており、薬物療法に加え、生活指導やリハビリテーションの提案も行います。
問診・診察
症状の内容や経過、ご家族の様子などを詳しく伺います。
検査
認知機能検査や神経学的検査、必要に応じて頭部CTなどの画像検査を行い、脳の状態を評価します。
診断・説明
検査結果をもとに原因や病態を丁寧に説明し、治療方針を決定します。
治療・対応
薬物療法に加え、生活習慣の改善指導、介護保険利用の相談など、症状に応じた総合的な対応を行います。
もの忘れは、年齢による自然な変化から、重大な疾患の兆候まで、さまざまな原因で起こります。「まだ早い」「様子を見てから」と先延ばしにせず、気になることがあれば早めにご相談ください。当院では、神経内科専門医、認知症専門医・指導医が在籍しております。丁寧に診察を行い、患者様一人ひとりに合った適切な対応を心がけています。
「加齢によるもの忘れ」である可能性が高いとは考えます。ただし、頻度が明らかに多い場合や日常生活への影響がある場合、他にも症状がある場合など、気になることがあれば一度ご相談ください。
認知症には進行を遅らせる治療や生活を支援する制度が利用できる場合があります。早期発見によって、より長く自立した生活を続けられる可能性があります。早めの対応が、安心につながります。
同じ話を繰り返す場合、記憶障害が起こっている可能性があります。受診をお勧めします。
はい。起こります。うつ病、ストレス、睡眠不足、甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏症などももの忘れを引き起こすことがあります。適宜、血液検査などを検討します。
ご本人のみでも受診は可能です。しかし、同居の方やご家族からの情報は診断にとても役立ちます。できる限り、ご一緒の来院をおすすめします。
問診や簡単な認知症の検査(HDS-R:改訂長谷川式簡易知能評価やMMSE:Mini Mental State Examinationなど)を行います。必要に応じて血液検査・頭部CT検査などで脳の状態を確認します。
症状の程度や治療内容によって異なります。一般的には1〜2ヶ月ごとの定期受診が多いです。
TOP